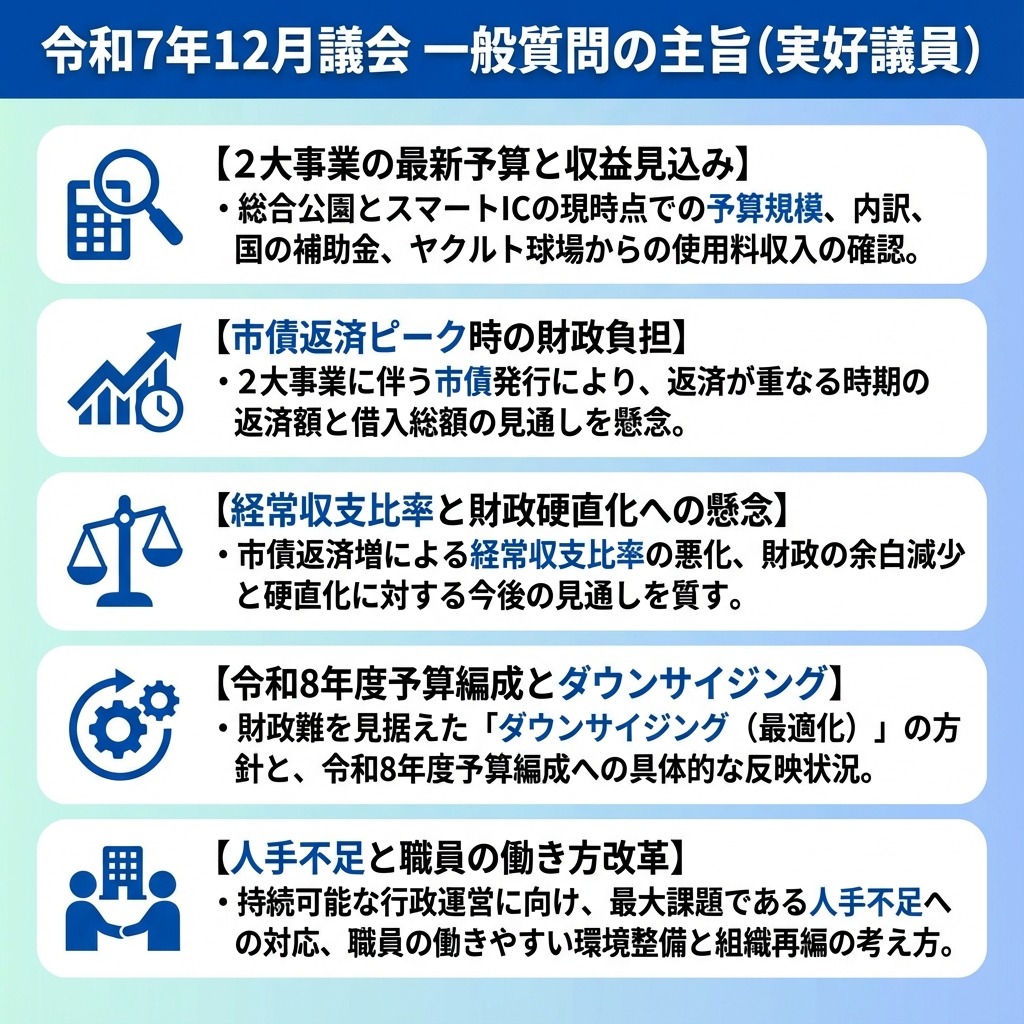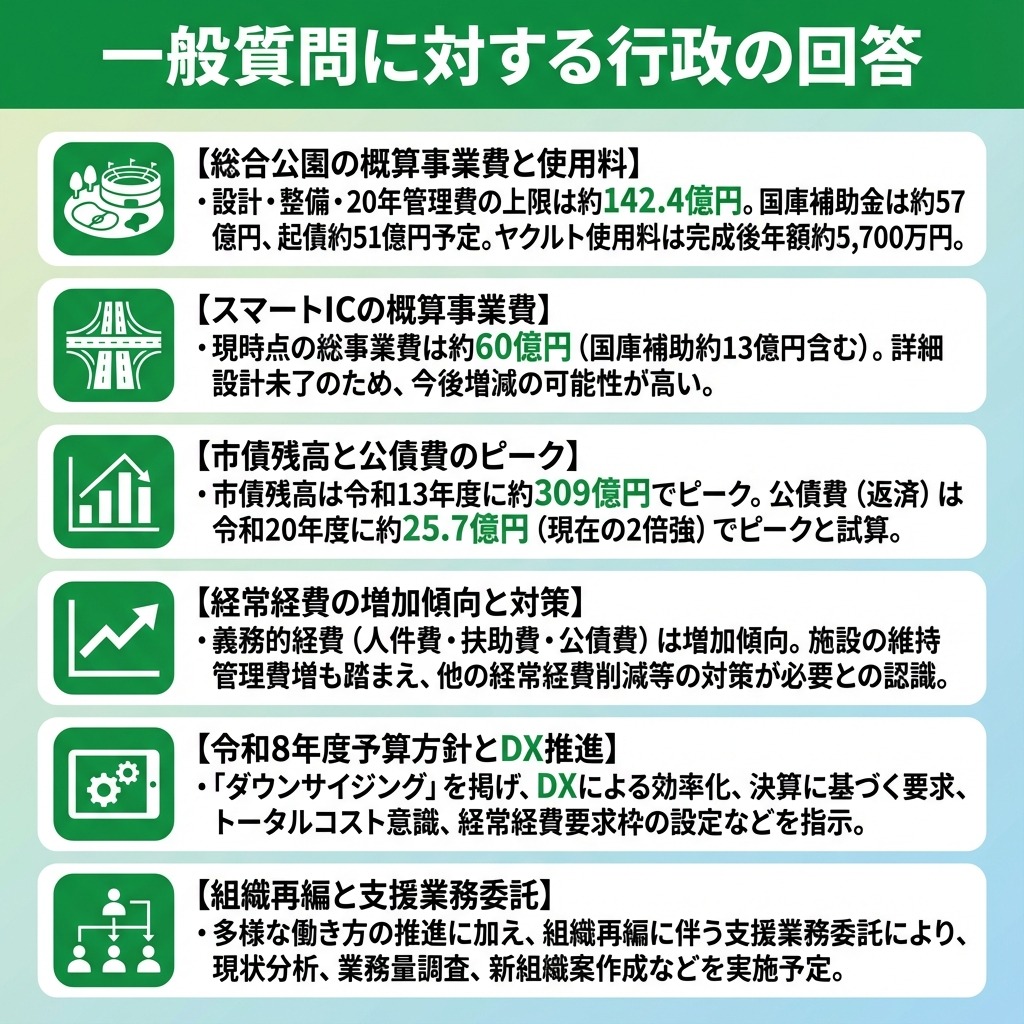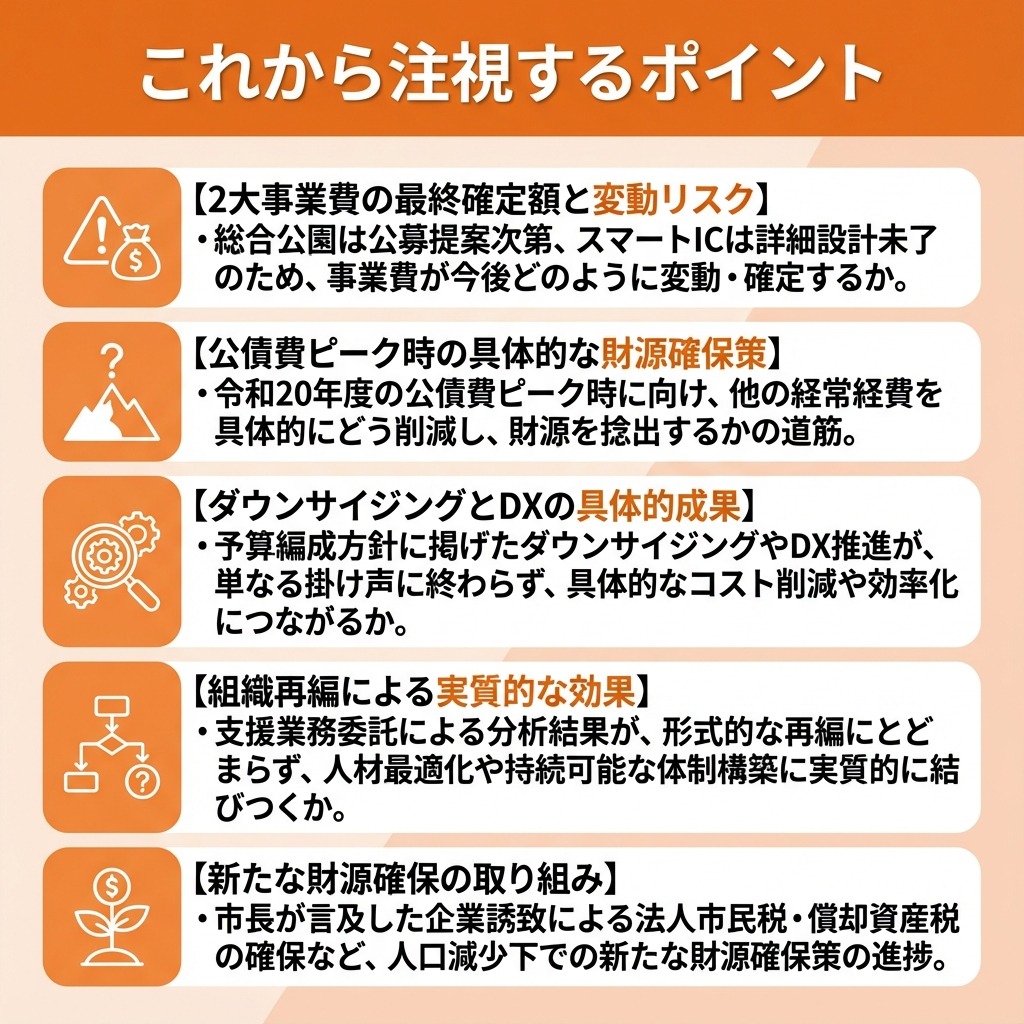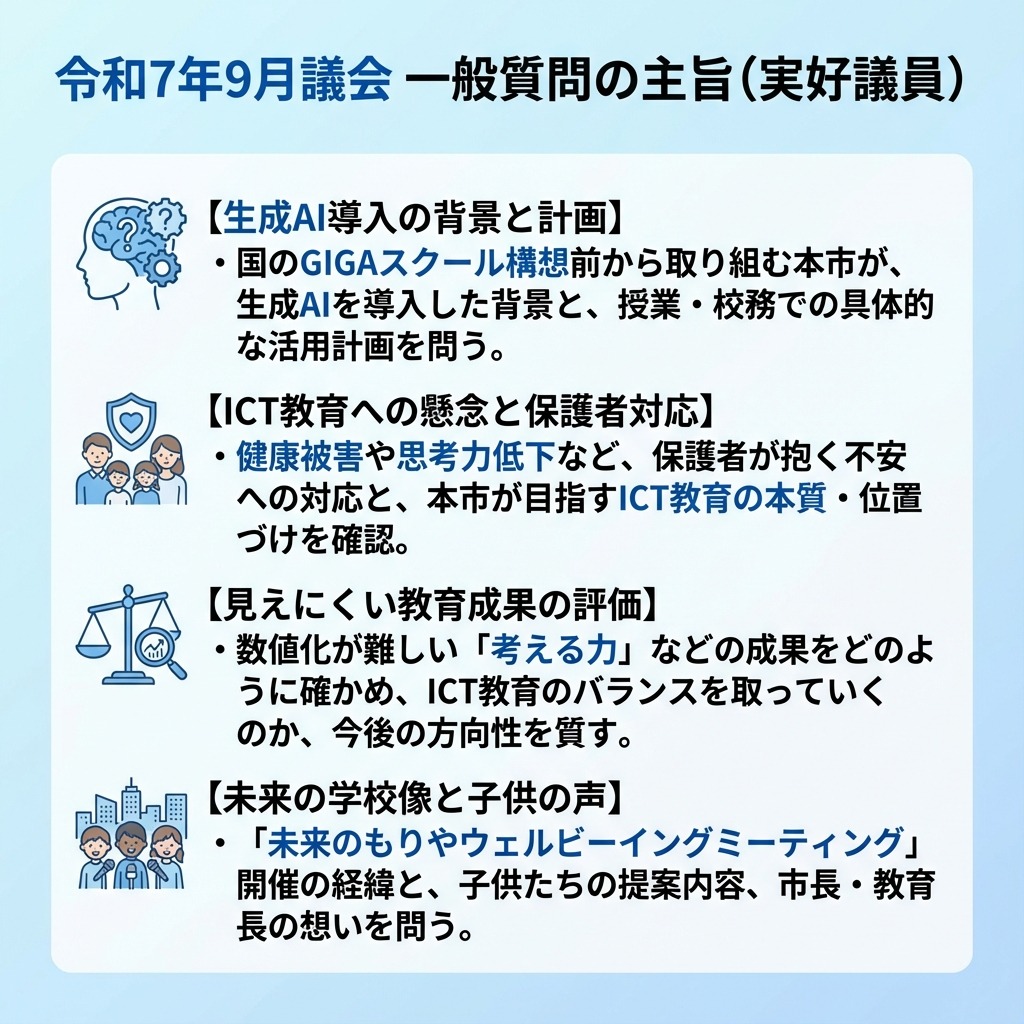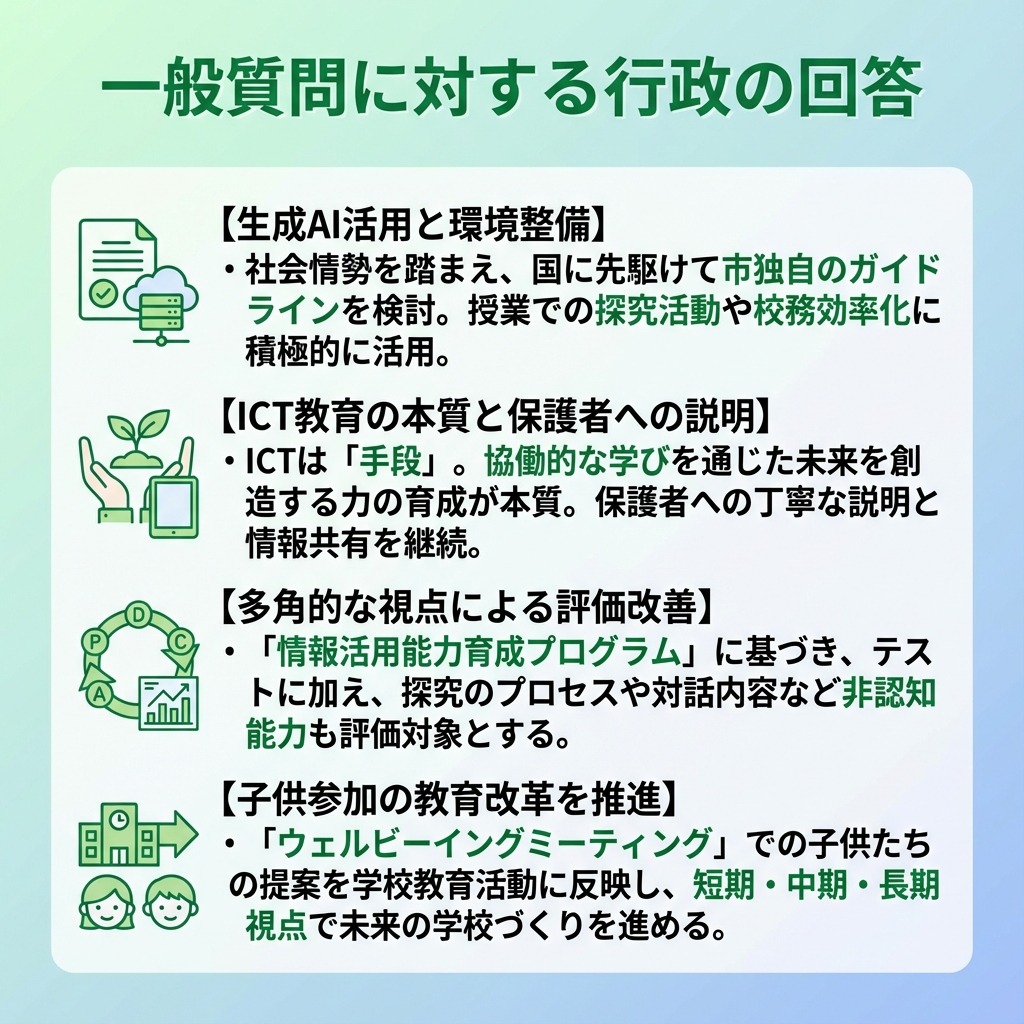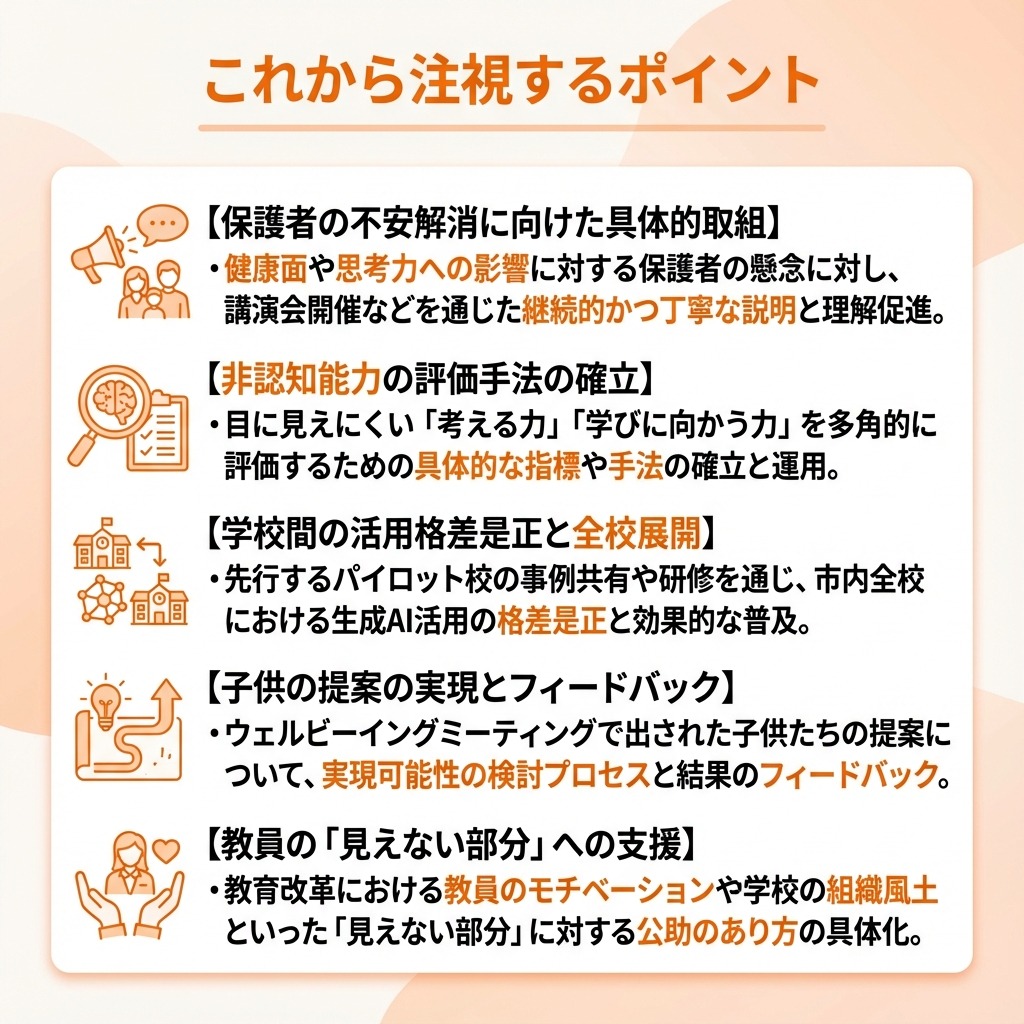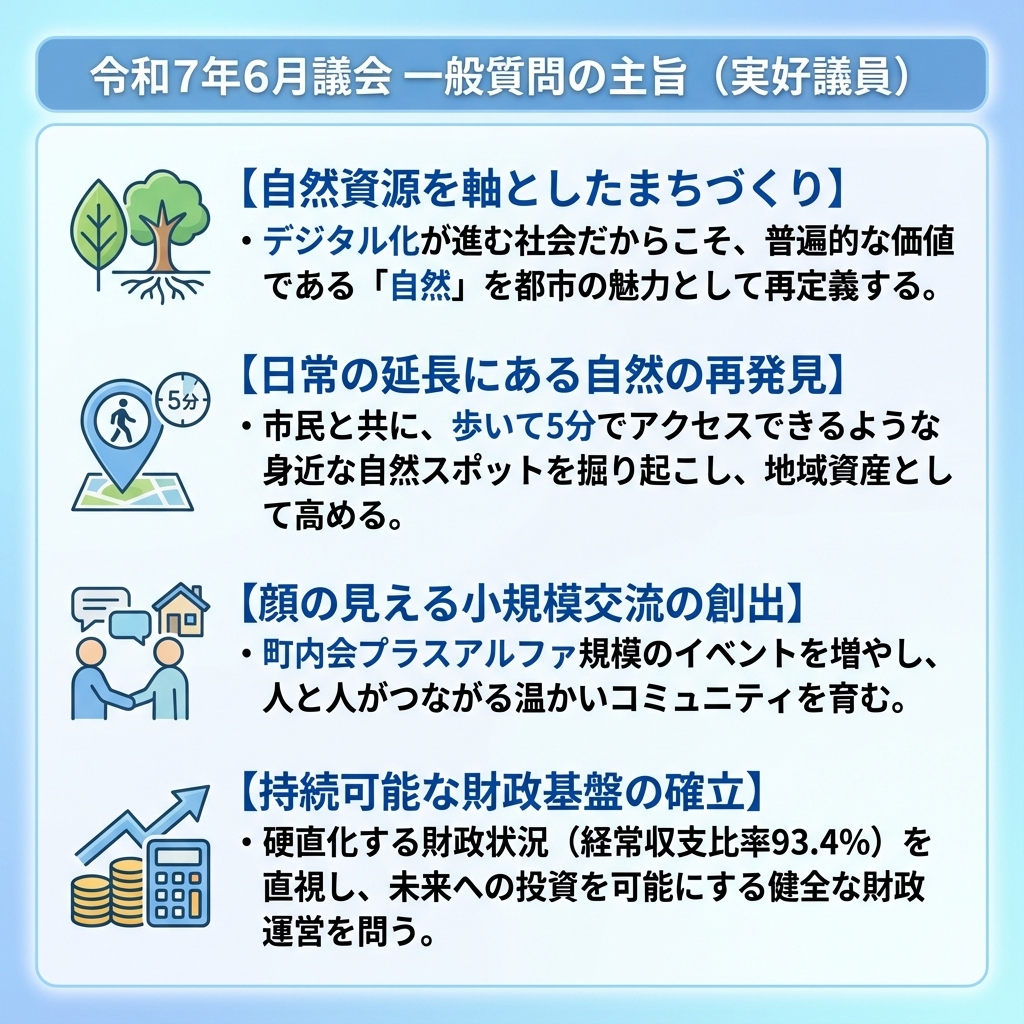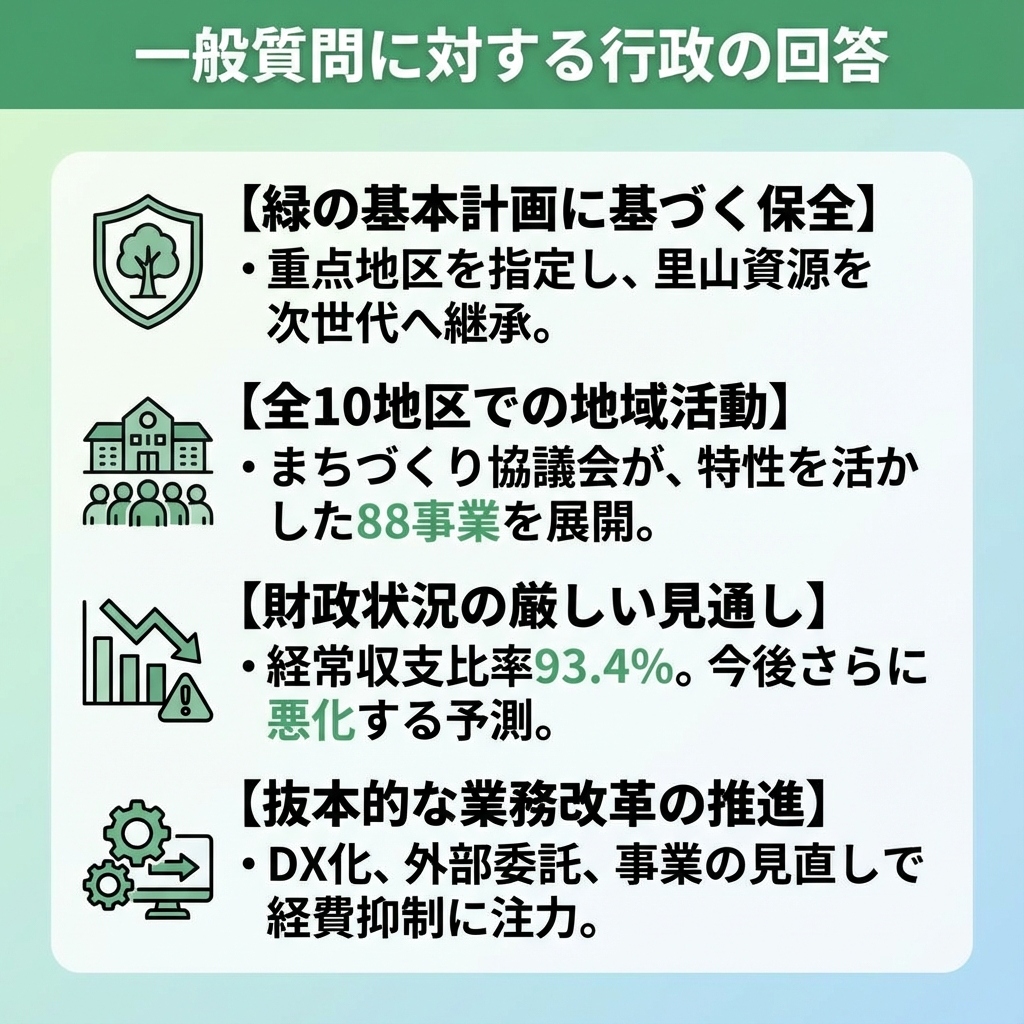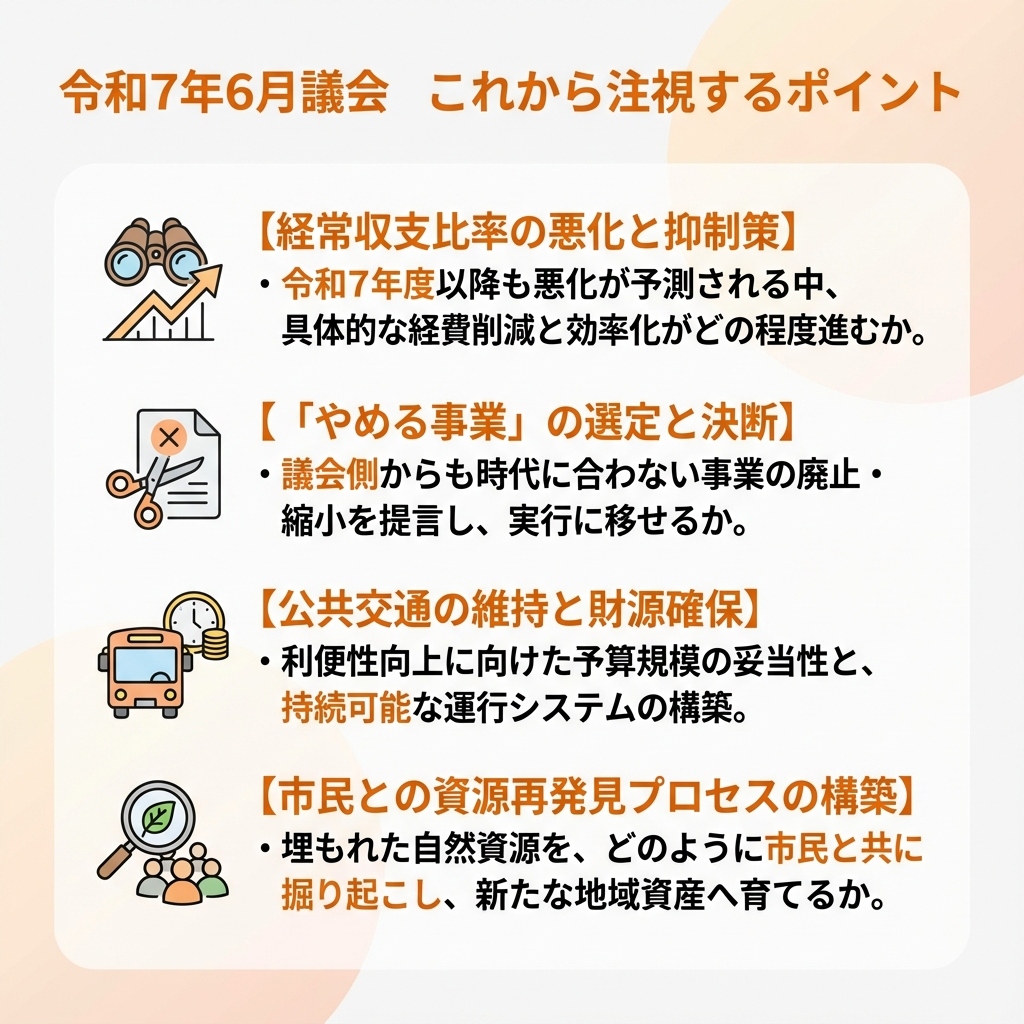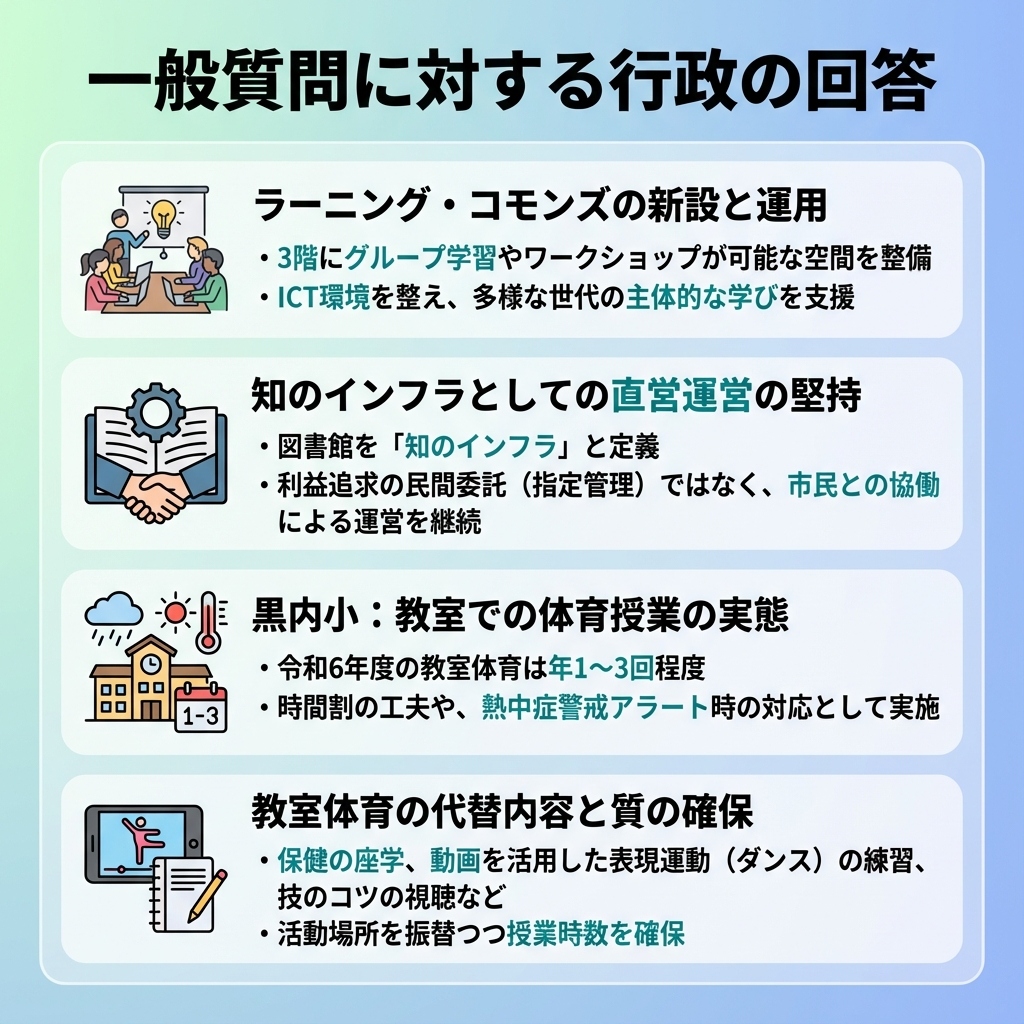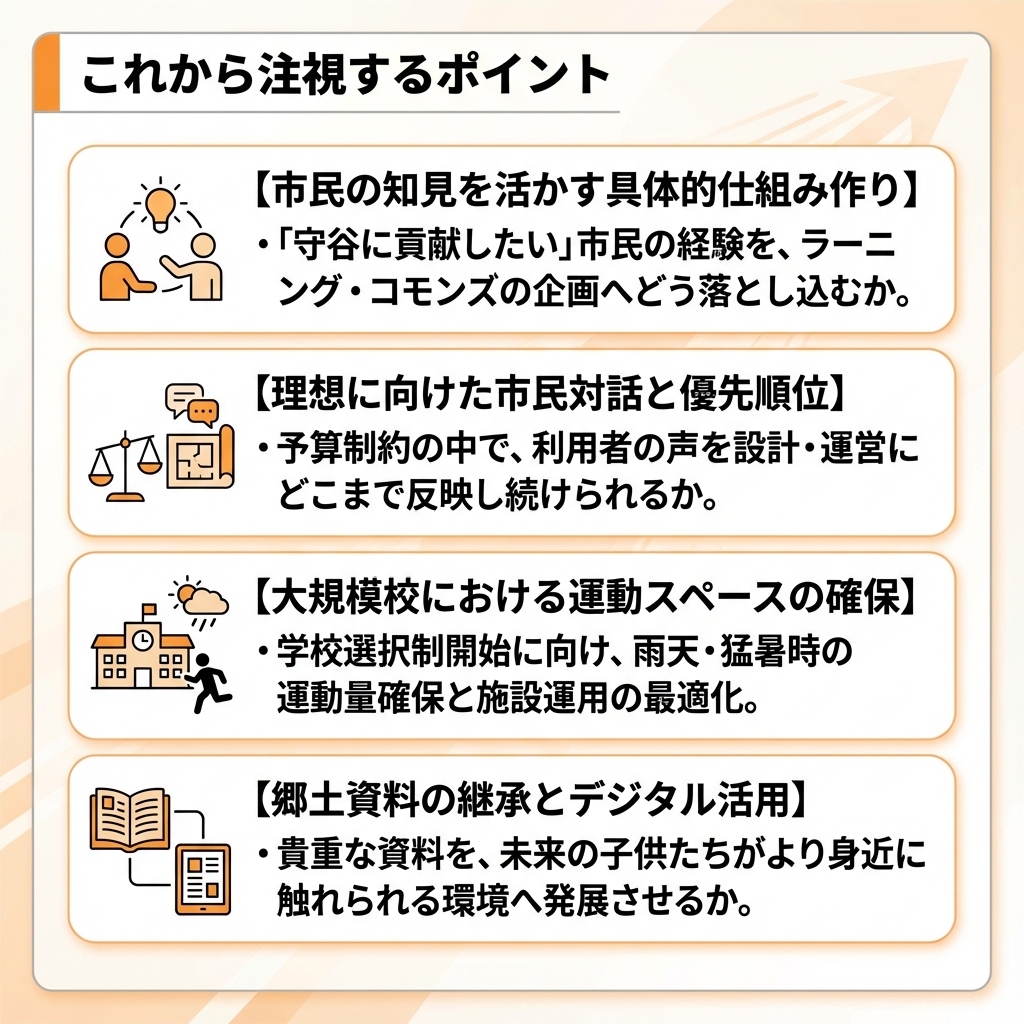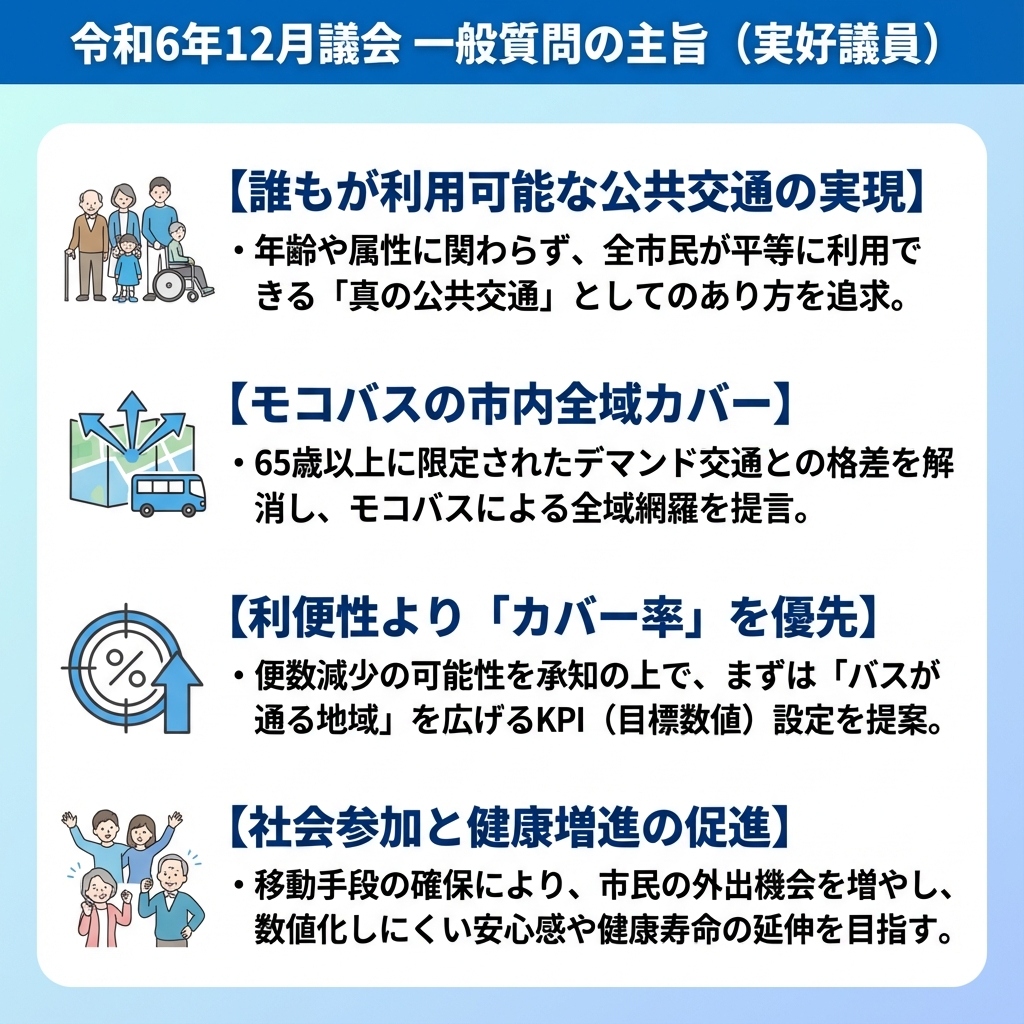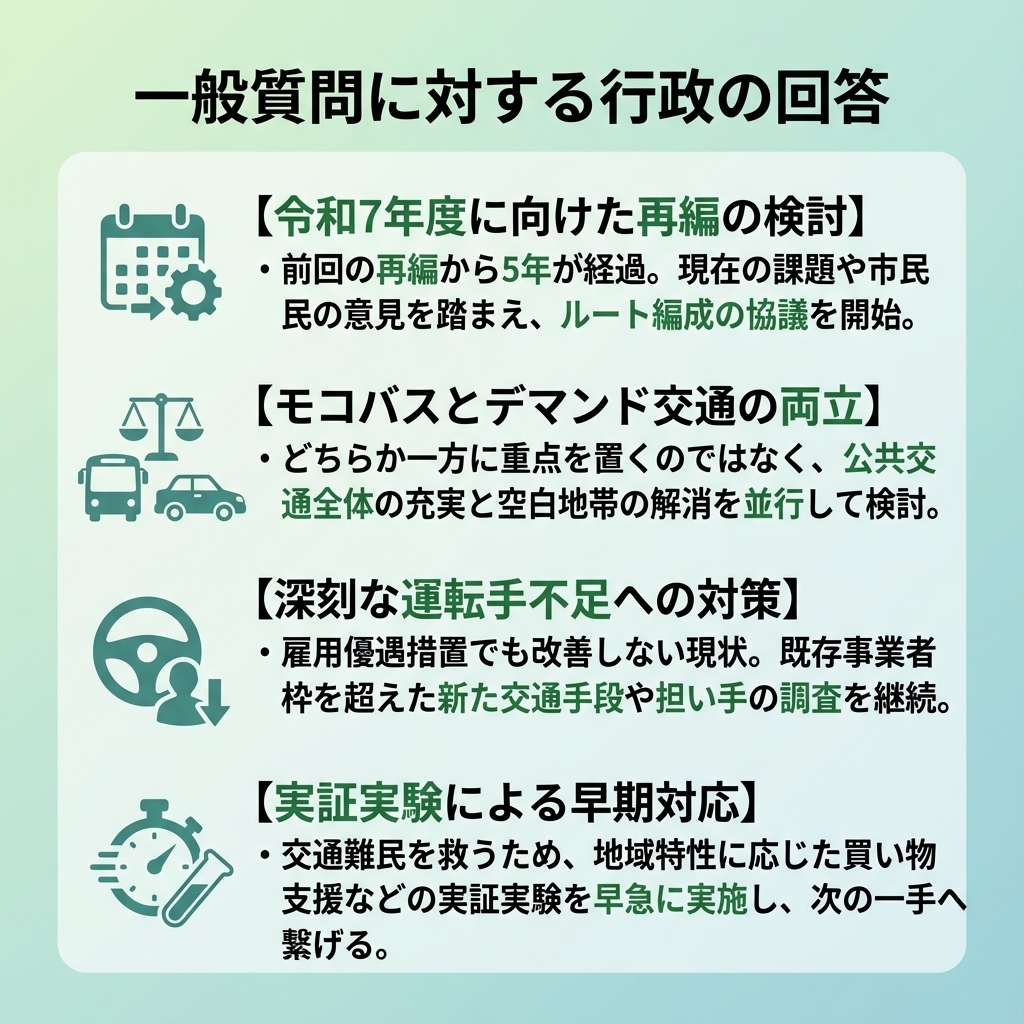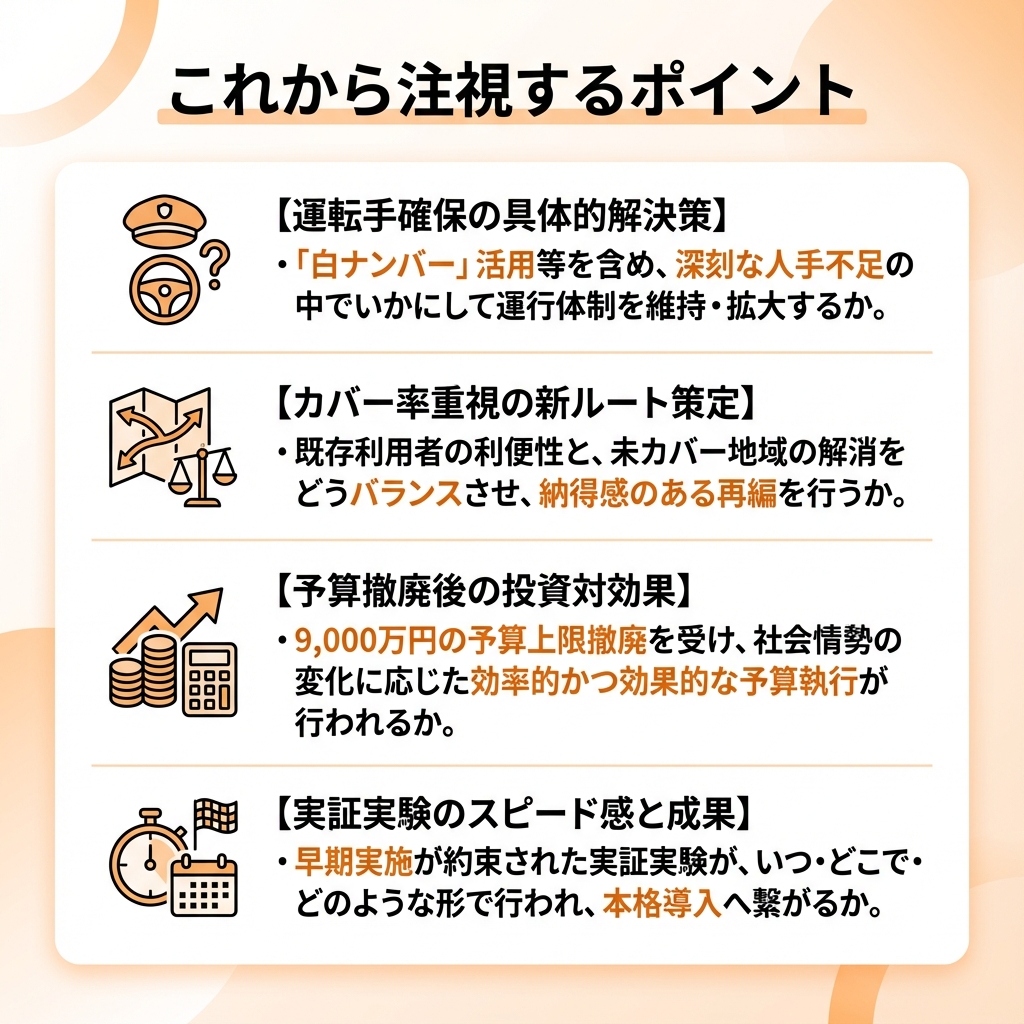一般質問

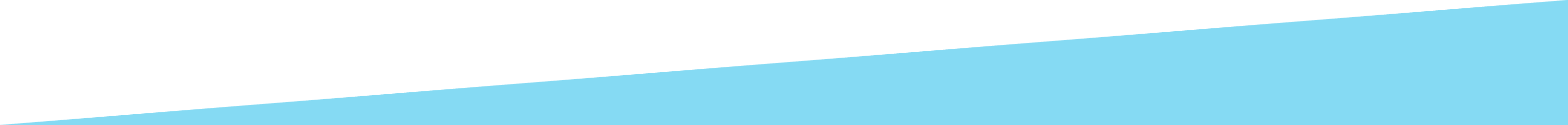
令和7年12月
守谷市のこれからの財政について
- ・2大事業の予算規模と内訳
- ・将来の財政負担と健全性指標
- ・行政運営の最適化と働き方改革
令和7年9月
守谷のみらいの教育について
- ・生成AIの教育活用
- ・ICT教育のこれから
- ・守谷のみらいの学校像
令和7年 6月議会
守谷のまちづくり戦略
- ・守谷のまちづくり戦略(自然資源の活用)
- ・守谷駅東口エリアの充実にむけて
- ・デジタル民主主義を体験!夏休みスペシャル企画
令和7年 3月議会
図書館改修と黒内小学校の教育環境
- ・図書館大規模改修と新機能
- ・黒内小学校の分離新設に向けた検討
令和6年 12月議会
守谷市の公共交通(モコバス)について
- ・モコバスの利便性向上策
- ・デマンド型交通との連携強化
- ・公共交通ネットワークの再構築
応援メッセージ
「ひとこと応援したい!」
そんな温かいメッセージも励みになります。